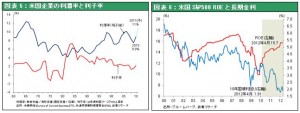過剰反応の日本株式
ギリシャ選挙における反緊縮策を主張する左翼勢力の躍進により、昨年末一旦封じ込まれた欧州通貨危機が再燃した。市場はギリシャの離脱が引き金となり、スペイン、ポルトガルなどへの危機波及、ユーロの崩壊といった最悪シナリオを織り込み始めている。世界株式市場は急落、日本株式も国内景気や企業収益に何ら不安はないのに、年初来の20%の上昇がほぼ帳消しとなった(図表1参照)。昨年と同様の展開である。ただしギリシャでは反緊縮を唱える急進左派連合の組閣が不調に終わり、6月17日再選挙がおこなわれる運びとなった。経済的観点からはどの角度から見ても、ギリシャにとって緊縮財政の受け入れによって債務免除を認めてもらいユーロに残留することの方が望ましいし、ギリシャ国民も大半がユーロ残留を望んでいるとの世論調査結果が出ている。ギリシャのユーロ離脱は回避される可能性が強いのではないか。その場合、売り込まれた世界株式は急反発する可能性が強い。日本株式の過剰反応ほどは、南欧諸国金利やソブリンCDSスプレッド、クレジットリスクプレミアムが上昇しているわけではない(図表3,4参照)。
欧州セーフティーネット、米国経済の二つが昨年とは異なる
Sell in May and go awayと言う米国相場格言そのままの展開であるが、昨年のように秋口まで調整が長引くことはなく、6月後半から力強いサマーラリーに入る可能性が大きい。二つの点で昨年とは大きく異なる。第一にユーロ内で危機の根源にある銀行の資産状況は把握され、ECB(欧州中央銀行)による無制限融資とESM(欧州安定化メカニズム)と言う二つのセーフティーネットが確立しており、最悪の銀行の連鎖破たんは起きないであろう(図表2参照)。第二に米国経済は、特に住宅環境が改善し、二番底の懸念がほぼ無くなっていると考える。
図表1:主要国相対株価(2009年3月=100)
図表2:ECB総資産推移
図表3:EU各国長期金利
図表4:EU各国のソブリンCDSプレミアム

万一、ギリシャ選挙の結果が緊縮策放棄とユーロからの離脱になったとしても、それが直ちにスペイン、ポルトガルに波及するわけではなかろう。ECBを経由したファイナンスとESMの活用により、金融危機の伝染を遮断できる可能性は大きい。フランス大統領選挙における社会党オランド大統領の勝利、米キャンプデービットG8での成長政策推進の確認などにより、政策の重点は財政再建よりは成長に移っている。それは成長懸念から不安を強めている市場に対しては、安心感を与えるものとなる可能性がある。
不安心理の根源、「金融資本主義の崩壊」シナリオ
それにしてもこの市場の自信のなさはなぜなのだろうか。金融資本主義の崩壊シナリオが根底にあるのだろう。リーマン・ショックからユーロ危機へと続く困難の原因は、金融資本主義による過剰なレバレッジという同根の錬金術にあり、そのつけは容易には解消できないという不安である。確かに日本だけではなく、米国、ドイツ、イギリスも史上空前の低金利時代に入っている。現象だけ見るとバブル生成と崩壊、その後の景気後退と空前の金利低下は、日本の「失われた20年」そのものであり、その意味で日本はフロントランナーに見える。であれば、欧米のデフレ、長期経済停滞は不可避と映る。リーマン・ショック後ボトム比1.8倍の米国株は「偽りの夜明け」に浮かれているに過ぎず、ほぼ横ばいの日本株が正しいという解釈になる。
金余り、人余りは負の後遺症ではなく、将来発展の手段
そうした悲観論の陥穽は、利潤率と利子率の極端なかい離を説明できない点にある(図表5,6参照)。確かに長期金利が大きく低下し、それは空前の金融緩和と同時に進行している。従って緊急避難的な金融緩和が行き場のない余剰資本をもたらしているとの解釈が正しく見える。しかし、他方で企業収益は世界的に好調で、米国ではリーマン・ショックの一年後には過去最高となるなど、利潤率が大きく上昇している。この潤沢な利益を投資に回さないから資本余剰が起きている。またITバブル、リーマン・ショック、ユーロ危機と経済困難を経るたびに、労働分配率が低下し企業収益を大きく押し上げている。企業は人と資本を使わずに儲かるようになり、人と資本が余っている。そうした経済資源の余剰は金融資本主義や過剰な金融緩和とは無縁のことである。何故なら省力、省資本こそ現在のグローバリゼーションとインターネット革命がもたらした、世界規模の産業革命(世界的規模の労働と資本の生産性向上)の落とし子だからである。
余剰資本と余剰労働力こそ人類発展の母であったことを考えると、我々は負の後遺症に囚われていると考えるのではなく、将来発展の手段を手にしていると考えるべきであろう。日本は余剰資本と余剰労働力を過去の負の遺産と捉えて、手をこまねき、デフレに陥ったが、同様の道を米国や欧州が辿るかどうか、何も宿命論的に考える必要はないだろう。
図表5:米国企業の利潤率と利子率
図表6:米国S&P500 ROEと長期金利
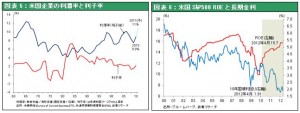
潤沢な民間貯蓄が徐々に需要を創造へ
米国では空前の好企業収益が続いており、家計貯蓄率もリーマン・ショック前の1%台から4%へと大きく上昇しているなど民間貯蓄は過去最高である。企業は余剰資金の多くを自社株買いに充て、自社株買いの時価総額に対する比率は4%にのぼり、米国株式の配当利回りの2%を加えると、企業は時価総額の6%を投資家に対して還元している状況である。ただ需要と雇用は本調子ではなく、リーマン・ショック以前の過剰消費の状態から一転、リーマン・ショック後は、むしろ過少消費状況にあるといえる。住宅投資の対GDP比率は、リーマン・ショック以前のピーク時で6%あったが、現在は2.3%まで落ち込んでいる。自動車販売台数も1,400万台程度で、過去の水準から見ても低いままである。この需要低迷の原因は、資金が無いためではなく、貯蓄を増やして消費を抑制しているのであるから、心理状態に問題があるといえる。ない袖は振れないと言うが、今の米国は袖はあるのに振っていない状態である。
心理改善の鍵、住宅に曙光、流通在庫急低下
よって、心理抑制要因が解かれるか否かが重要となるが、長らく重石となり続けてきた住宅情勢の反転を確認することが決定的に重要であろう。先ず流通在庫が大きく減少してきた。抵当で差し押さえられた住宅物件が住宅価格を引き下げる要因となってきたが、流通在庫月数が大きく低下してきた(図表7)。
住宅価格も、様々な観点から著しく割安となっている。住宅価格に対する所有者賃借料比率が、過去最低水準にあること、名目GDPに対する家計保有不動産時価の割合は、1990年代の1.2倍から2000年代のピーク時で1.9倍まで上昇し、現在は、再び1.2倍に戻っていること(図表8)、住宅取得能力指数も、1990年代は120~140の間で推移、その後の住宅バブルにより100まで低下、現在は過去最高の200台にまで上昇している事、などである(図表9)。住宅ローン金利の空前の低下も、長期的な住宅を購入するチャンスを示唆している。
持家比率底入れへ
需給悪化の陰の主役であった持ち家比率はピーク時(2004年末)には69.2%に達したが、現在は65.4%へと急低下し、底入れ気配が濃厚である(図表10)。クリントン、ブッシュ政権において、オーナーシップ・ソサエティが推進され、住宅取得がブームとなったことから持ち家比率が上昇、そして、サブプライムローンが低所得者の持ち家取得を支えたのであった。その後、バブル崩壊により持ち家比率が急速に低下して、住宅需給が悪化した。しかし、住宅保有による税制面や金融面のメリットに変わりはない。したがって、どこかで底入れし、回復する状況に転じるはずである。1984年に持ち家比率が低下から回復に転じた局面があったが、2012年も同様の状況になると期待される。このように危機の中心にあった住宅情勢の改善が確かになったことは、米国経済の復活、デフレ回避の可能性を高めるものである。
図表7:米国中古住宅販売月数
図表8:米国家計保有不動産時価/名目GDPと10年国債利回り
図表9:米国住宅買いやすさ指数
図表10:米国持家比率

 万一、ギリシャ選挙の結果が緊縮策放棄とユーロからの離脱になったとしても、それが直ちにスペイン、ポルトガルに波及するわけではなかろう。ECBを経由したファイナンスとESMの活用により、金融危機の伝染を遮断できる可能性は大きい。フランス大統領選挙における社会党オランド大統領の勝利、米キャンプデービットG8での成長政策推進の確認などにより、政策の重点は財政再建よりは成長に移っている。それは成長懸念から不安を強めている市場に対しては、安心感を与えるものとなる可能性がある。
万一、ギリシャ選挙の結果が緊縮策放棄とユーロからの離脱になったとしても、それが直ちにスペイン、ポルトガルに波及するわけではなかろう。ECBを経由したファイナンスとESMの活用により、金融危機の伝染を遮断できる可能性は大きい。フランス大統領選挙における社会党オランド大統領の勝利、米キャンプデービットG8での成長政策推進の確認などにより、政策の重点は財政再建よりは成長に移っている。それは成長懸念から不安を強めている市場に対しては、安心感を与えるものとなる可能性がある。